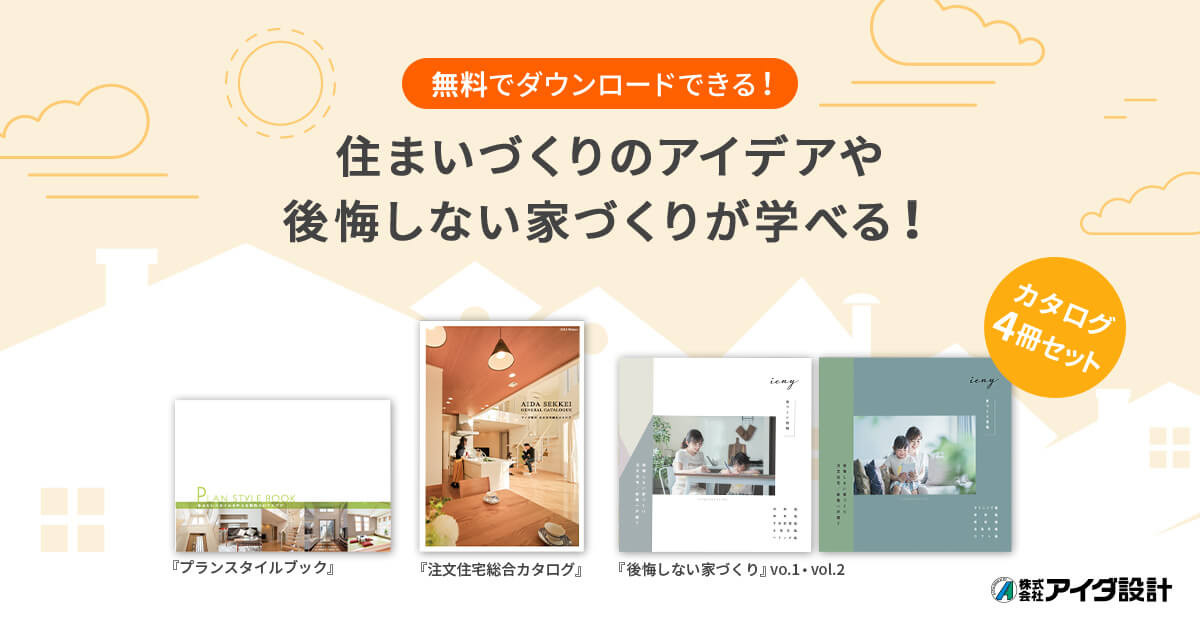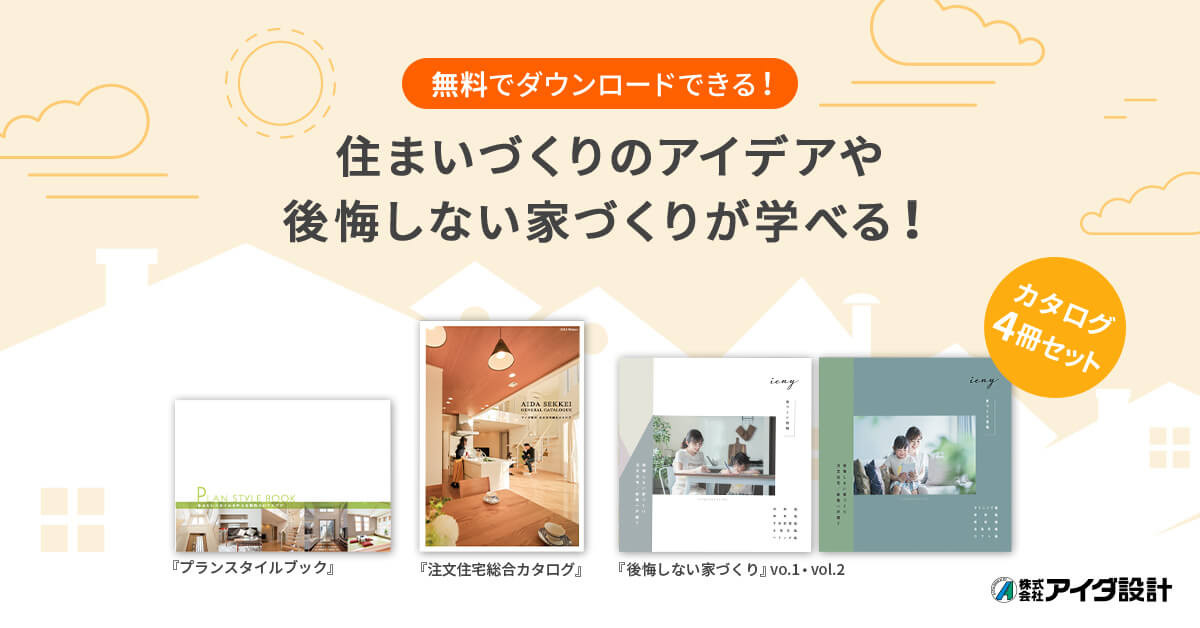T構造? H構造? 同じ木造住宅でも火災保険料が違う?
火災保険料は燃えにくい建物ほど安くなることを知っていますか?

つまり、木造住宅よりも、コンクリート構造や鉄筋造りの建物の方が保険料は安くなるということ。では、木造住宅はすべて高い保険料を払わなくてはいけないのかというと、それも少し違います。
同じ木造住宅でも耐火構造であるT構造と非耐火構造であるH構造とでは、支払う火災保険料に差が生じるとされています。
T構造とH構造や気になる火災保険料について詳しく見ていきましょう!
◇お家の保険の話はこちらをチェック
災害のときに補償をしてくれる「住宅保険」で知りたいこと
では、T構造とH構造の具体的な違いはどこにあるのでしょうか。
「T構造」とは、耐火構造のことをさします。「耐火」の頭文字のTを用いられた用語になります。
T構造に該当するのは、 1. 共同住宅で耐火建築物ではないもの
2. 一戸建てで柱がコンクリート、レンガ、石、鉄骨で造られているもの
3. 一戸建てで耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建物に該当するもの
の3つになります。
耐火建築物とは、建築基準法第2条9号の2に定める耐火建築物で、主要構造部(柱・はり・床・屋根など)が耐火構造であること、一定の耐火性能の技術的基準に適合する建物のことをさします。
木造建築でも外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等を有するなどの耐火構造をとっていれば、準耐火建築物として認定されます。詳しくは担当者などに質問をするとよいでしょう。
非耐火構造の頭文字の「H」から名付けられた用語です。主に、T構造とM構造(マンション構造)に含まれない建物のことをさします。
木造建築で特に火災対策が施されていないお家は、こちらに該当すると考えてよいでしょう。
保険料は耐火性があるT構造が安く、非耐火性となるH構造が高く設定されています。
構造判定において注意すべき物件もあるので、確かな判定や正しい判断は専門家に相談して、詳しく調べてもらってください。
ちなみに、火災保険の構造区分は3区分となっており、ご説明したT構造・H構造のほかに「M構造」というものもあります。
M構造とは「マンション構造」の頭文字「M」から名付けられた用語です。主に鉄筋コンクリート造で建てられたマンションや共同住宅が該当し、耐火建築物の共同住宅もM構造に含まれます。

家の構造によって、火災のリスクや損害は変化します。そのため、火災保険料の金額にも違いが生じるのです。
建物の構造級別とは、構造を示す区分に従って判定をおこなうものです。前段で詳しく解説をしていますが、まず建物の種類は住宅の柱の材料や共同住宅かなどを確認、また法令上の建物の性能を確認します。
T構造(耐火構造)の方が、H構造(非耐火構造)に比べて、比較的保険料が安くなります。また、住み始めたときのままの保険料でも、その後増築や改築、一部取り壊し等をおこなうことで、保険料に変化が生じる場合も。
その際には契約変更の手続きが必要となるので、ハウスメーカーや専門家への相談を欠かさないようにしてください。
家は日々、変化していくもの。それに合わせて、保険なども細かく見直していく必要があります。
省令耐火構造の住宅とは、建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構が定める基準に適合する住宅のことです。
この省令準耐火構造の家として基準を満たしているとされている住宅の一つに「ツーバイフォー」という工法で建てられた家があります。
ツーバイフォー工法とは、木造の建築工法のこと。フレーム上に組まれた木材の骨組みに合板を打ち付けたものをパネル化し、壁・床・天井として6面体に組み合わせて「面」で支えます。ほかには「枠組壁工法」と呼ばれることも。
地震や強風など、外から加わる力を面で受け止めることができるため、一般的に頑丈で耐火のほかにも、耐震・気密・断熱などにも強いとされています。
ツーバイフォーなどの省令準耐火構造の住宅は「T構造」に格上げされ、保険料が大幅に安くなり、地震保険への加入もしやすくなります。
ちなみに、地震保険はT構造やH構造に関係なく、火災保険に加入した方のみが加入できる保険です。その保険金額は火災保険の30~50%と決まっています。詳しくは、こちらの記事でご紹介しているので、ぜひ確認してみてくださいね。

木造住宅の中でも高建築物や省令準耐火住宅などにすることでT構造に該当させることができます。
一般的な木造住宅は非耐火構造のH構造に分類されるので、火災保険料の金額が大きく異なってしまいます。木造建築でも、きちんと火災対策をすることで丈夫で長持ちをさせることができますし、支払う保険料金が抑えられ、大きな節約にもつながります。といっても、これからお家を建てるという場合、その多くがT構造になっているはず。そこまで大きな心配をする必要はないかもしれません。担当の方への確認をオススメします。
同じ木造住宅でも、耐火性に優れたT構造と非耐火性のH構造の住宅では性能も火災保険料も全く異なります。
火災保険は、万が一を想定して加入する保険ですが、しっかり商品内容を確認し、住みはじめてから手を加えて構造に変化が発生した時には、早めに保険会社へ連絡をするようにしてください。
きちんとご自宅の構造について調べておくことで、いざという時に役立つことがあるかもしれません。
災害に備えて防災グッズなどを揃えると共に、お家の構造についても家族みんなでの事前確認がオススメです。
■地震・火災に強い木造住宅のご相談はハウスメーカー・アイダ設計へ。自社の木材カット工場で製材した材料を使い、最長35年保証も実現。
木造住宅をお考えの方はぜひご相談ください。
→WEBでのご相談はこちらから
→アイダ設計の注文住宅・建築事例を見る
→アイダ設計の注文住宅を詳しく
<参考元>
日本損害保険協会 - 損害保険Q&A - すまいの保険 - 問58 火災保険
そういったさまざまな自然災害に見舞われたとき、家族の安全を守ってくれる家づくりに真摯に向き合って誕生したのがアイダ設計の「対策に真摯に向き合っている「セーフティハウス プラス」。
建築基準法1.5倍の耐震性である「耐震等級3」の標準化や台風対策のためのシャッターの設置など、まさに家族の安全な暮らしを守るための工夫が盛りだくさんとなっています。
せっかく家を建てるなら、永く安全に暮らしたい! そんな願いを叶える「セーフティーハウス プラス」。ぜひ、チェックしてみてくださいね。
【安心・安全を守る家づくり】アイダ設計の「セーフティーハウス プラス」とは?

つまり、木造住宅よりも、コンクリート構造や鉄筋造りの建物の方が保険料は安くなるということ。では、木造住宅はすべて高い保険料を払わなくてはいけないのかというと、それも少し違います。
同じ木造住宅でも耐火構造であるT構造と非耐火構造であるH構造とでは、支払う火災保険料に差が生じるとされています。
T構造とH構造や気になる火災保険料について詳しく見ていきましょう!
◇お家の保険の話はこちらをチェック
災害のときに補償をしてくれる「住宅保険」で知りたいこと
T構造とH構造って何?
ご自身の家の構造タイプを知っておくことは、とても大切。なぜなら、物件の構造によって火災保険料の金額には差が生じるためです。では、T構造とH構造の具体的な違いはどこにあるのでしょうか。
T構造
「T構造」とは、耐火構造のことをさします。「耐火」の頭文字のTを用いられた用語になります。
T構造に該当するのは、 1. 共同住宅で耐火建築物ではないもの
2. 一戸建てで柱がコンクリート、レンガ、石、鉄骨で造られているもの
3. 一戸建てで耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建物に該当するもの
の3つになります。
耐火建築物とは、建築基準法第2条9号の2に定める耐火建築物で、主要構造部(柱・はり・床・屋根など)が耐火構造であること、一定の耐火性能の技術的基準に適合する建物のことをさします。
木造建築でも外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等を有するなどの耐火構造をとっていれば、準耐火建築物として認定されます。詳しくは担当者などに質問をするとよいでしょう。
H構造
非耐火構造の頭文字の「H」から名付けられた用語です。主に、T構造とM構造(マンション構造)に含まれない建物のことをさします。
木造建築で特に火災対策が施されていないお家は、こちらに該当すると考えてよいでしょう。
保険料は耐火性があるT構造が安く、非耐火性となるH構造が高く設定されています。
構造判定において注意すべき物件もあるので、確かな判定や正しい判断は専門家に相談して、詳しく調べてもらってください。
ちなみに、火災保険の構造区分は3区分となっており、ご説明したT構造・H構造のほかに「M構造」というものもあります。
M構造とは「マンション構造」の頭文字「M」から名付けられた用語です。主に鉄筋コンクリート造で建てられたマンションや共同住宅が該当し、耐火建築物の共同住宅もM構造に含まれます。
T構造とH構造の保険料の具体的な違いって?

家の構造によって、火災のリスクや損害は変化します。そのため、火災保険料の金額にも違いが生じるのです。
建物の構造級別とは、構造を示す区分に従って判定をおこなうものです。前段で詳しく解説をしていますが、まず建物の種類は住宅の柱の材料や共同住宅かなどを確認、また法令上の建物の性能を確認します。
T構造(耐火構造)の方が、H構造(非耐火構造)に比べて、比較的保険料が安くなります。また、住み始めたときのままの保険料でも、その後増築や改築、一部取り壊し等をおこなうことで、保険料に変化が生じる場合も。
その際には契約変更の手続きが必要となるので、ハウスメーカーや専門家への相談を欠かさないようにしてください。
家は日々、変化していくもの。それに合わせて、保険なども細かく見直していく必要があります。
「省令準耐火構造の家」とは?
「T構造」が耐火建築物であるということはご理解いただけましたか? しかし、ここで気になるのはT構造のなかに含まれる「省令準耐火構造」というもの。省令準耐火構造の家とはどんなものなのでしょうか?省令耐火構造の住宅とは、建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構が定める基準に適合する住宅のことです。
この省令準耐火構造の家として基準を満たしているとされている住宅の一つに「ツーバイフォー」という工法で建てられた家があります。
ツーバイフォー工法とは、木造の建築工法のこと。フレーム上に組まれた木材の骨組みに合板を打ち付けたものをパネル化し、壁・床・天井として6面体に組み合わせて「面」で支えます。ほかには「枠組壁工法」と呼ばれることも。
地震や強風など、外から加わる力を面で受け止めることができるため、一般的に頑丈で耐火のほかにも、耐震・気密・断熱などにも強いとされています。
ツーバイフォーなどの省令準耐火構造の住宅は「T構造」に格上げされ、保険料が大幅に安くなり、地震保険への加入もしやすくなります。
ちなみに、地震保険はT構造やH構造に関係なく、火災保険に加入した方のみが加入できる保険です。その保険金額は火災保険の30~50%と決まっています。詳しくは、こちらの記事でご紹介しているので、ぜひ確認してみてくださいね。
木造住宅を建てるならT構造!

木造住宅の中でも高建築物や省令準耐火住宅などにすることでT構造に該当させることができます。
一般的な木造住宅は非耐火構造のH構造に分類されるので、火災保険料の金額が大きく異なってしまいます。木造建築でも、きちんと火災対策をすることで丈夫で長持ちをさせることができますし、支払う保険料金が抑えられ、大きな節約にもつながります。といっても、これからお家を建てるという場合、その多くがT構造になっているはず。そこまで大きな心配をする必要はないかもしれません。担当の方への確認をオススメします。
同じ木造住宅でも、耐火性に優れたT構造と非耐火性のH構造の住宅では性能も火災保険料も全く異なります。
火災保険は、万が一を想定して加入する保険ですが、しっかり商品内容を確認し、住みはじめてから手を加えて構造に変化が発生した時には、早めに保険会社へ連絡をするようにしてください。
きちんとご自宅の構造について調べておくことで、いざという時に役立つことがあるかもしれません。
災害に備えて防災グッズなどを揃えると共に、お家の構造についても家族みんなでの事前確認がオススメです。
■地震・火災に強い木造住宅のご相談はハウスメーカー・アイダ設計へ。自社の木材カット工場で製材した材料を使い、最長35年保証も実現。
木造住宅をお考えの方はぜひご相談ください。
→WEBでのご相談はこちらから
→アイダ設計の注文住宅・建築事例を見る
→アイダ設計の注文住宅を詳しく
<参考元>
日本損害保険協会 - 損害保険Q&A - すまいの保険 - 問58 火災保険
アイダ設計が提案! 家族の暮らしを守る「セーフティハウス プラス」
さまざまな自然災害に見舞われることもある日本。家を建てる際には火災はもちろんですが、地震対策などもしっかりと行っておきたいものです。そういったさまざまな自然災害に見舞われたとき、家族の安全を守ってくれる家づくりに真摯に向き合って誕生したのがアイダ設計の「対策に真摯に向き合っている「セーフティハウス プラス」。
建築基準法1.5倍の耐震性である「耐震等級3」の標準化や台風対策のためのシャッターの設置など、まさに家族の安全な暮らしを守るための工夫が盛りだくさんとなっています。
せっかく家を建てるなら、永く安全に暮らしたい! そんな願いを叶える「セーフティーハウス プラス」。ぜひ、チェックしてみてくださいね。
【安心・安全を守る家づくり】アイダ設計の「セーフティーハウス プラス」とは?
必要事項をご記入の上、
「資料を請求する」を押してください。
※は必須入力項目です。
【プライバシーポリシー】
個人情報の利用目的
このフォームに入力いただきました個人情報は、資料のお届けのほかに、以下の目的で利用させて頂く場合がございます。
- ①当社事業(不動産分譲事業、注文建築事業)等の営業活動における訪問、ダイレクトメール、電話、電子メールによる勧誘
- ②顧客動向調査、商品開発等の為の分析
- ③当社の商品やサービスの紹介や宣伝
- ④アフターサービス、定期メンテナンスの為の工事委託
- ⑤保険媒介代理事業
- ⑥ローン媒介代理業務
- ⑦その他当社の事業に付帯・関連する事項
その他個人情報の取り扱いについては、当社HPにてご確認ください。
https://www.aidagroup.co.jp/company/info/privacy.html