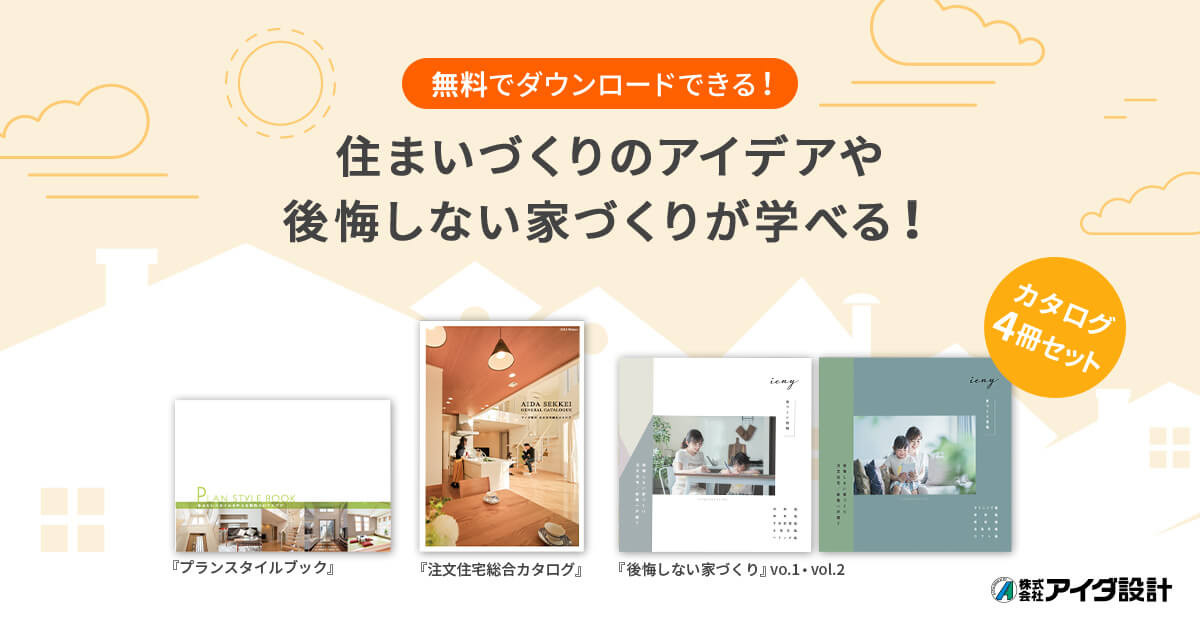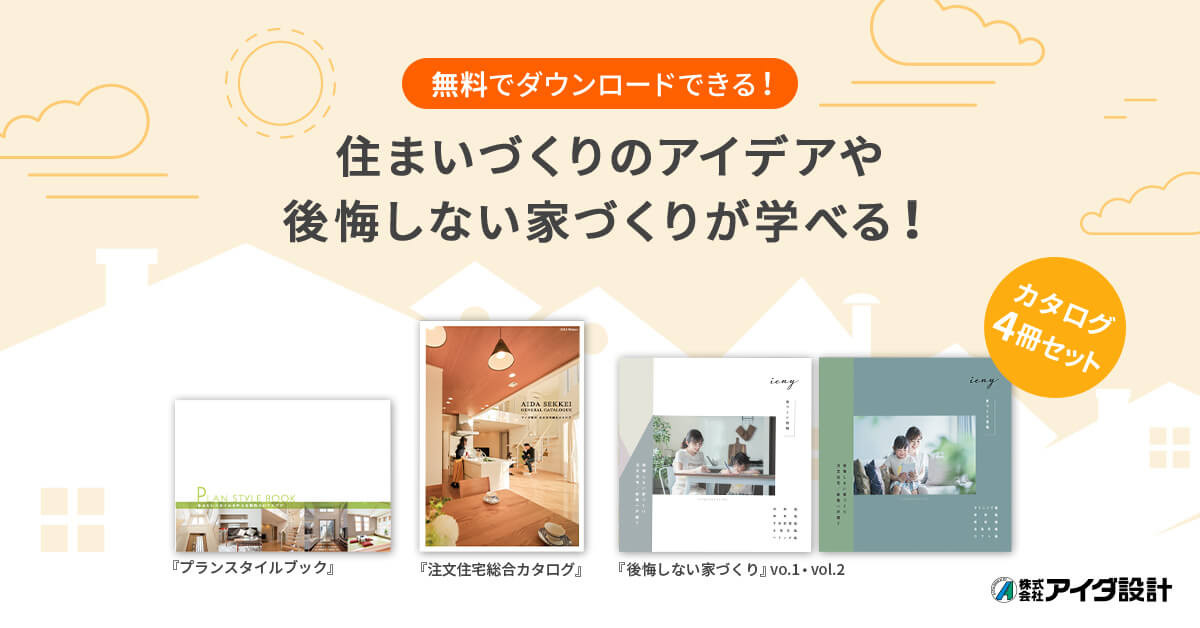実は明るさが足りていない? 部屋の明るさ不足を解消する照明選びのポイント
家を建てるなら、家具や照明などのインテリアにこだわって、オシャレな空間づくりを叶えたいですよね。雰囲気のよい間接照明やスポットライトをインテリアに使えば、陰影が重なって写真映えするアクセントになって素敵な雰囲気に!
しかし、その照明は実は「明るさが足りていない」状態かもしれません。ほんの数時間を過ごすカフェやレストランなら問題ない明るさでも、毎日過ごす自宅の照明としては生活の質を落としてしまう可能性が……。

「ちょっと暗いかな? と感じるくらいの方が落ち着く」
「好きなインテリアを優先して照明を選びたい! 」
そうお考えの方にこそ知ってほしい「明るさ不足を解消する一戸建ての照明選び」について紹介します!
それが「JIS照明基準総則(JIS Z9110-2010)」で、「ジス」と読みます。「JIS」はJapanese Industrial Standardsの略で、日本産業規格という国家規格で定められた共通規格です。
人が「安全・容易かつ快適に」活動できるように、住宅をはじめ事務所、工場、学校、商業施設や美術館、ホテル、駅、公園など日常生活を送るさまざまなシーンで必要な明るさの基準を照度(lx:ルクス)という単位で規定しています。

表を見てわかるように、同じ「居間=リビングルーム」でも手芸や裁縫なら1000lx、読書なら500lx、団らん・娯楽なら200lxと、必要な明るさは全く異なります。1000lxがどれくらい明るいかというと「晴れた日の日没1時間前の太陽光」と同じ程度です。つまり真昼の光ではないとはいえ、晴れた日の屋外と同じ明るさが必要ということです。
また、この基準は健康な成人を基準にしていますから、高齢者など視力が低い人が過ごす部屋となると、さらに明るさが必要になることもあります。
「家のなかはリラックスできるように、少し暗く感じるくらいの雰囲気」だけで照明選びをすると、さまざまな作業に支障が出るかもしれません。

照明器具の選定には6つのポイントがあります。総合的にチェックしていきましょう。
同じ照明器具でも、天井の高さや広さ、壁の色や窓の位置などによって得られる明るさは異なります。照明選びが家づくりの最終ステップになるのは、そのためでもあります。
意外と忘れがちなのが、家全体を通じた明るさのバランスです。暗いところから明るいところへ急に出た場合、まぶしくて一瞬視界が悪くなったり、逆に明るいところから暗い所へ移動すると目が慣れるまで真っ暗で何も見えなくなったりします。
それと同じように、家のなかでも明るさの差があまりにも大きいと、事故や怪我の原因にも。明るさの比が2倍以内に収まるよう、リビングから廊下、さらにトイレや寝室、階段などの明るさのバランスを整えましょう。
電球には「色温度」と呼ばれる光の色を表す単位があります。オレンジ色の暖色系を電球色から、太陽の光に近い昼白色、青みがかった白でしっかり見える昼光色などがあります。
LEDはこの色温度を調節できるため、特にリビングやダイニングなど時間と目的によって使い方が変化する場所によく使用されます。
明かりにこだわる方の多くは「インテリアとしての照明」を重視されているのではないでしょうか。
もちろん心地よい暮らしを実現するためにも、デザイン性は大切ですよね。このときのポイントは、明かりとしてのメイン照明となるシーリング照明ではなく、ダウンライトやブラケット、スタンドライトなどのサブ照明でアクセントをつけるということです。うまく取り入れて、理想のインテリアを叶えましょう。
照明器具は毎日使うものです。スマートホームと組み合わせれば、リモコンやパネルを使わず音声で照明のオン・オフができますし、タイマーや遠隔からの操作も可能になります。
たとえば家の外からスマホで「子ども部屋の照明がついているから、もう帰宅しているんだな」とチェックできたり、旅行の際外灯や玄関の照明を外部から点けることができたりと、新しい照明機器ならではの便利さもチェックしておきましょう。
家の照明器具をLEDと蛍光灯で比較すると、

照明には用途や場所によって必要な明るさの基準があり、その基準を満たす照明を組み合わせて使うこと、用途や時間に応じて明るさを調整できることが必要となります。
しかし、明るさは単に電球のワット数の足し算では測れないため、選んだり確認したりといったことをすべて自分で行うことはなかなか難しいでしょう。
「感覚的に照明を選ぶ」のではなく、必要な明るさを確保した主照明は設計のプロに一般的な照明の組み合わせをオススメしてもらい、補助照明やその明るさを確保できる照明器具選定に好みを反映させるのが安心ですよ!
>>わが家だけのインテリアを照明で実現! 【照明タイプ別のメリット・デメリット】
>>【一級建築士が解説】“業者任せ”で後悔しがち! 注文住宅の照明とコンセントの決め方

全国で分譲住宅を展開中のハウスメーカー・アイダ設計が展開する、「パターンオーダー住宅」。なんと100パターンの間取りからわが家の暮らしにフィットした家づくりを実現できる「パターンオーダー住宅」を選ぶことができます。

これは建売住宅と注文住宅の間に位置するプラン。建築する土地が用意されており、その土地に合わせた間取りプランや外観を選ぶことができるものです。
コストを抑えながら、建売ではない自分たちに合ったプランで家づくりができます。
>> アイダ設計のパターンオーダー住宅、分譲住宅情報はコチラ
エリアや沿線、価格帯などの条件で土地も検索できますのでぜひ一度ご確認ください。
>>100パターンの間取りが用意された、新・分譲住宅「パターンオーダー住宅」
>>おしゃれな家を適正価格で!「デザイナーズ規格住宅」~デザイン監修・建築家 宮下信顕氏インタビュー
そんな家づくり初心者の方にピッタリなのが、今だけ無料プレゼントしているアイダ設計の家づくりのアイデアやヒントがいっぱい詰まったカタログ『プランスタイルブック』。
 リビングをランクアップ! プレミアムTVコーナー
リビングをランクアップ! プレミアムTVコーナー
 フォトスタンドや小物を置いて「魅せる収納」に! ディスプレイ収納
フォトスタンドや小物を置いて「魅せる収納」に! ディスプレイ収納
無料ダウンロードができ、間取り図と写真・解説が付いているので、さらに理想の住まいがイメージしやすくなるはず!申し込みは記事下のフォームから。
メールアドレスの登録だけで、カンタンにカタログのダウンロードができます。完全自由設計の注文住宅をローコストで実現するアイダ設計なら、こうしたアイデアの提案が得意。経験豊富な設計士が一から図面を起こすので、さまざま工夫が敷地の面積や形にあった形で実現できます。
お問い合わせやご相談は無料。ぜひこちらからお気軽にご相談ください。
アイダ設計の注文住宅の事例を見る
しかし、その照明は実は「明るさが足りていない」状態かもしれません。ほんの数時間を過ごすカフェやレストランなら問題ない明るさでも、毎日過ごす自宅の照明としては生活の質を落としてしまう可能性が……。

「ちょっと暗いかな? と感じるくらいの方が落ち着く」
「好きなインテリアを優先して照明を選びたい! 」
そうお考えの方にこそ知ってほしい「明るさ不足を解消する一戸建ての照明選び」について紹介します!
必要な明るさの基準とは
住宅照明に必要な明るさには、明確な基準があります。それが「JIS照明基準総則(JIS Z9110-2010)」で、「ジス」と読みます。「JIS」はJapanese Industrial Standardsの略で、日本産業規格という国家規格で定められた共通規格です。
人が「安全・容易かつ快適に」活動できるように、住宅をはじめ事務所、工場、学校、商業施設や美術館、ホテル、駅、公園など日常生活を送るさまざまなシーンで必要な明るさの基準を照度(lx:ルクス)という単位で規定しています。
住宅で規定されている照度を確認しよう

表を見てわかるように、同じ「居間=リビングルーム」でも手芸や裁縫なら1000lx、読書なら500lx、団らん・娯楽なら200lxと、必要な明るさは全く異なります。1000lxがどれくらい明るいかというと「晴れた日の日没1時間前の太陽光」と同じ程度です。つまり真昼の光ではないとはいえ、晴れた日の屋外と同じ明るさが必要ということです。
また、この基準は健康な成人を基準にしていますから、高齢者など視力が低い人が過ごす部屋となると、さらに明るさが必要になることもあります。
「家のなかはリラックスできるように、少し暗く感じるくらいの雰囲気」だけで照明選びをすると、さまざまな作業に支障が出るかもしれません。
何を優先して明かりを選ぶ?

照明器具の選定には6つのポイントがあります。総合的にチェックしていきましょう。
その場所に必要な明るさ
同じ照明器具でも、天井の高さや広さ、壁の色や窓の位置などによって得られる明るさは異なります。照明選びが家づくりの最終ステップになるのは、そのためでもあります。
家全体を通した明るさのバランス
意外と忘れがちなのが、家全体を通じた明るさのバランスです。暗いところから明るいところへ急に出た場合、まぶしくて一瞬視界が悪くなったり、逆に明るいところから暗い所へ移動すると目が慣れるまで真っ暗で何も見えなくなったりします。
それと同じように、家のなかでも明るさの差があまりにも大きいと、事故や怪我の原因にも。明るさの比が2倍以内に収まるよう、リビングから廊下、さらにトイレや寝室、階段などの明るさのバランスを整えましょう。
光の色の演出
電球には「色温度」と呼ばれる光の色を表す単位があります。オレンジ色の暖色系を電球色から、太陽の光に近い昼白色、青みがかった白でしっかり見える昼光色などがあります。
LEDはこの色温度を調節できるため、特にリビングやダイニングなど時間と目的によって使い方が変化する場所によく使用されます。
インテリアとしての照明
明かりにこだわる方の多くは「インテリアとしての照明」を重視されているのではないでしょうか。
もちろん心地よい暮らしを実現するためにも、デザイン性は大切ですよね。このときのポイントは、明かりとしてのメイン照明となるシーリング照明ではなく、ダウンライトやブラケット、スタンドライトなどのサブ照明でアクセントをつけるということです。うまく取り入れて、理想のインテリアを叶えましょう。
設備としての扱いやすさ
照明器具は毎日使うものです。スマートホームと組み合わせれば、リモコンやパネルを使わず音声で照明のオン・オフができますし、タイマーや遠隔からの操作も可能になります。
たとえば家の外からスマホで「子ども部屋の照明がついているから、もう帰宅しているんだな」とチェックできたり、旅行の際外灯や玄関の照明を外部から点けることができたりと、新しい照明機器ならではの便利さもチェックしておきましょう。
電気代とエコ
家の照明器具をLEDと蛍光灯で比較すると、
- LEDは導入費用は高いものの、その後の電気代が安い
- 電球の寿命が3~4倍と長く、交換の手間も費用も抑えることができる
快適に暮らすために目的と場所に応じた照明を選ぼう

照明には用途や場所によって必要な明るさの基準があり、その基準を満たす照明を組み合わせて使うこと、用途や時間に応じて明るさを調整できることが必要となります。
しかし、明るさは単に電球のワット数の足し算では測れないため、選んだり確認したりといったことをすべて自分で行うことはなかなか難しいでしょう。
「感覚的に照明を選ぶ」のではなく、必要な明るさを確保した主照明は設計のプロに一般的な照明の組み合わせをオススメしてもらい、補助照明やその明るさを確保できる照明器具選定に好みを反映させるのが安心ですよ!
>>わが家だけのインテリアを照明で実現! 【照明タイプ別のメリット・デメリット】
>>【一級建築士が解説】“業者任せ”で後悔しがち! 注文住宅の照明とコンセントの決め方
分譲住宅でもわが家らしいを叶える“パターンオーダー住宅”

全国で分譲住宅を展開中のハウスメーカー・アイダ設計が展開する、「パターンオーダー住宅」。なんと100パターンの間取りからわが家の暮らしにフィットした家づくりを実現できる「パターンオーダー住宅」を選ぶことができます。

これは建売住宅と注文住宅の間に位置するプラン。建築する土地が用意されており、その土地に合わせた間取りプランや外観を選ぶことができるものです。
コストを抑えながら、建売ではない自分たちに合ったプランで家づくりができます。
>> アイダ設計のパターンオーダー住宅、分譲住宅情報はコチラ
エリアや沿線、価格帯などの条件で土地も検索できますのでぜひ一度ご確認ください。
>>100パターンの間取りが用意された、新・分譲住宅「パターンオーダー住宅」
>>おしゃれな家を適正価格で!「デザイナーズ規格住宅」~デザイン監修・建築家 宮下信顕氏インタビュー
初めてでも後悔しない家づくり! プロのアイデアにおまかせ
家づくりは、初めてのことが盛りだくさん。家事がラクになる間取りにしたい! 収納スペースはどれくらいあればいいの? など、お悩みもたくさん出てきてしまいますよね。そんな家づくり初心者の方にピッタリなのが、今だけ無料プレゼントしているアイダ設計の家づくりのアイデアやヒントがいっぱい詰まったカタログ『プランスタイルブック』。
 リビングをランクアップ! プレミアムTVコーナー
リビングをランクアップ! プレミアムTVコーナー  フォトスタンドや小物を置いて「魅せる収納」に! ディスプレイ収納
フォトスタンドや小物を置いて「魅せる収納」に! ディスプレイ収納無料ダウンロードができ、間取り図と写真・解説が付いているので、さらに理想の住まいがイメージしやすくなるはず!申し込みは記事下のフォームから。
メールアドレスの登録だけで、カンタンにカタログのダウンロードができます。完全自由設計の注文住宅をローコストで実現するアイダ設計なら、こうしたアイデアの提案が得意。経験豊富な設計士が一から図面を起こすので、さまざま工夫が敷地の面積や形にあった形で実現できます。
お問い合わせやご相談は無料。ぜひこちらからお気軽にご相談ください。
アイダ設計の注文住宅の事例を見る
必要事項をご記入の上、
「資料を請求する」を押してください。
※は必須入力項目です。
【プライバシーポリシー】
個人情報の利用目的
このフォームに入力いただきました個人情報は、資料のお届けのほかに、以下の目的で利用させて頂く場合がございます。
- ①当社事業(不動産分譲事業、注文建築事業)等の営業活動における訪問、ダイレクトメール、電話、電子メールによる勧誘
- ②顧客動向調査、商品開発等の為の分析
- ③当社の商品やサービスの紹介や宣伝
- ④アフターサービス、定期メンテナンスの為の工事委託
- ⑤保険媒介代理事業
- ⑥ローン媒介代理業務
- ⑦その他当社の事業に付帯・関連する事項
その他個人情報の取り扱いについては、当社HPにてご確認ください。
https://www.aidagroup.co.jp/company/info/privacy.html