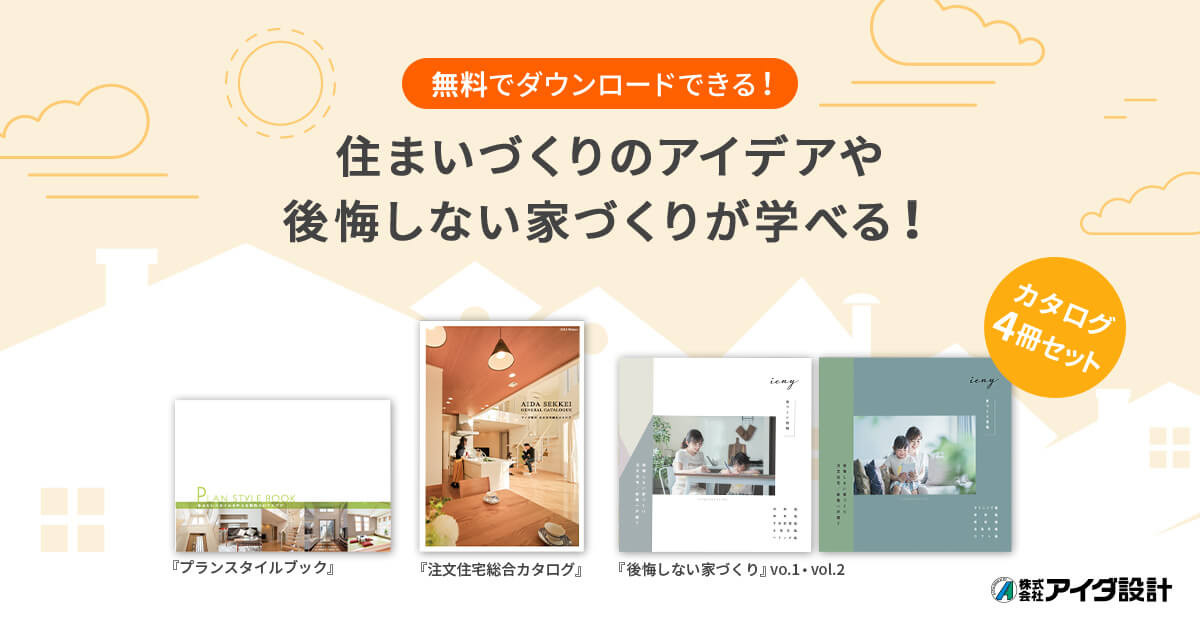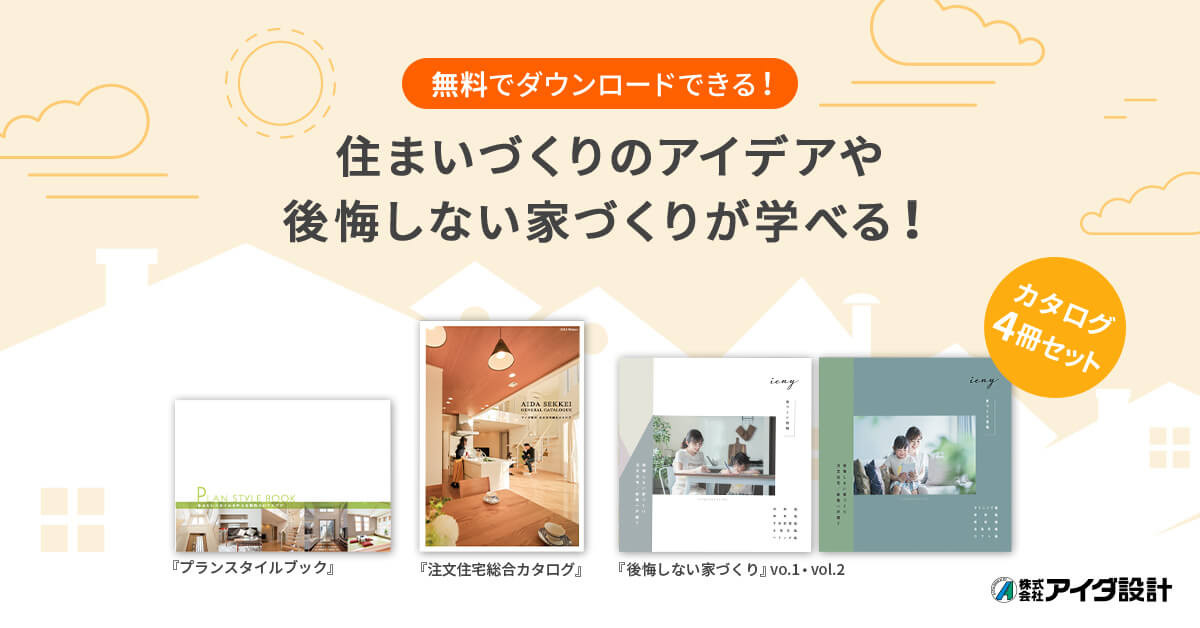【お宅訪問】無垢材は経年でどうなる?築17年の建築家の家で教えてもらいました
住宅の内装材として人気の「無垢材」。丸太から切り出した自然素材で肌触りがよく、美しい杢目が特長の一方で、メンテナンスの心配や、どのように経年変化していくかイメージしづらいところも悩ましいポイントです。

そこで今回は、無垢材をふんだんに取り入れた建築家のお宅を訪問! 無垢材の経年変化の状態や、どんな材種をどこに使っているのか適材適所のヒント、そしてお手入れ方法など、無垢材を取り入れた家づくりについて教えていただきました。

栗原さん(以下、K):ここは自宅兼モデルハウスで、住んで17年になります。
「エコロジー(Ecological)」「デザイン(Design)」「オーガニック(Organic)」をキーワードに江戸時代の自立循環型社会を参考にした家で、キーワードの頭文字をとって“EDO”、「江戸Styleの家」と名付けました。
土に還る自然素材を使った、住む人と環境にやさしい住まいです。
雨水タンクを設置して、雨水をトイレの水や屋根に流して夏場の暑さ対策に活用するなど、自然エネルギーを有効に利用したエコロジーな暮らしも提唱しています。
デザインは、江戸の“粋”を大切にしています。
江戸時代の暮らしから学びながら暮らそうというコンセプトで、4畳半+4畳半の小上がりの畳コーナーとダイニングは、夏は今のように開放的に、冬は小上がりの建具をしめて空間を分けて暖かく過ごすことができるようにしています。

K:木材は、宮城県栗原市と埼玉県飯能市の山の産地と協力しながら、国産材を使った家づくりをしています。宮城県とは、もう20年来のつきあいです。
それぞれ材種の特徴をふまえて、使い分けをします。建築主さまのお好みと予算に応じて選んでいきますが、私自身は個人的にスギが好きなので、スギが多めになっています。
材種別にご説明しましょう。
この家の床はカラマツ、建具はマツです。針葉樹のマツは、柔らかくて足腰に負担がかからないので、お年寄りの住宅の床にはオススメです。材料は違いますが、感じとしてはコルクタイルのようなものです。マツは、赤みが強くなります。

壁、天井、柱にスギを使っています。白みが強く、経年で年輪のところに赤みが出てくるのが味わいです。ここの天井は、2階の床を兼ねた杉のパネルです。梁を隠さず、大工さんの技を堪能できるのと、天井高を実現しています。

上がり框(かまち)にはヒノキを使っています。昔から日本で手に入るまっすぐな木材は、スギとヒノキだったため、柱にはスギかヒノキが使われてきました。ヒノキは、白みがいっぱいです。

広葉樹で、堅い木の雰囲気が好きな方に好まれます。黄色みが強く、明るい色が多いので若い方にも人気です。
この家では、お風呂にも無垢材を使っています。

浴槽は高野槇(マキ)の木のお風呂で、ふたはさわらの板。バスコートの床は、耐久性を持たせるために燻煙加工したくりこま杉。脱衣室の床は、藤タイルです。


また、最初は黄色かったり、白っぽかったりする色が、年が重なってくると美しく変わってくれます。飴色になる具合が、材種によって違うのも楽しみのひとつです。




K:自然素材だからといって、そんなに気を使ってメンテナンスをする必要はありません。この家では特に磨き込んだりなどはしておらず、自然の変化で飴色に変わってきた状態です。
メンテナンスは、床については水をはじくよう半年に一回くらいワックスがけを行います。雑巾がけの要領です。私は、天然原料で造るドイツの自然塗料メーカー・アウロのワックスをかけています。その他に特別なことはしていません。
また、自然素材の特徴として、木は生きているので湿度、熱の変化によって動くものです。
たとえば、この家のダイニングの床は床暖房になっています。湿度と熱の変化で、小さくなったり、大きくなったり。何年経っても、17年経った今でも動いています。でも、生活に支障がでるほどのことはありません。
そういうものとしてつきあっていく、自然素材の個性です。
K:もともとは自然素材の経年美化が美しいから自然素材の家を作っていましたが、15~20年くらい前から、シックハウスという問題に対して「自然素材の家」を提案してきました。
その自然な流れのなかで、省エネルギーな暮らし方を自然の素材を使った家づくりのなかで実現していきたいと思ってきました。
現代では法律が変わったり技術が変わったりして、防火地域、準防火地域でも4~5階建てのビルが木造で作れるようになってきました。学校や公共施設での木材使用も推奨されています。
輸入材に頼らず国産のもので賄うという機運もあり、需要が増えれば山の方も活性化してくると思います。
都会で木をつかうということは、産地の山を元気にすることでもあるし、木は二酸化炭素を吸って固定化していますので脱炭素にも貢献できることになります。
時代が変わりつつある、今がちょうど変わり目だと感じています。
――自然素材の無垢材を使うことで、持続可能な社会にも貢献できるのですね。本日は、ありがとうございました。
自然素材、国産材を活用した家づくりを続けて30年以上。コモン(共有・共用地)の考え方を取り入れた分譲地「江戸Styleの家づくり(入会地による雑木林の町角づくり)プロジェクト」が平成21年度国土交通省長期優良住宅先導的モデル事業に採択された。
https://www.kokyusumai.com/

写真提供:光設計
そこで今回は、無垢材をふんだんに取り入れた建築家のお宅を訪問! 無垢材の経年変化の状態や、どんな材種をどこに使っているのか適材適所のヒント、そしてお手入れ方法など、無垢材を取り入れた家づくりについて教えていただきました。
<お話を伺った方>
一級建築士/光設計・代表 栗原 守 さん
一級建築士/光設計・代表 栗原 守 さん
飴色に輝く無垢材の家
――本日は、ご自宅にお邪魔させていただきありがとうございます。まずはこちらのお住まいの特徴を教えてください。
栗原さん(以下、K):ここは自宅兼モデルハウスで、住んで17年になります。
「エコロジー(Ecological)」「デザイン(Design)」「オーガニック(Organic)」をキーワードに江戸時代の自立循環型社会を参考にした家で、キーワードの頭文字をとって“EDO”、「江戸Styleの家」と名付けました。
土に還る自然素材を使った、住む人と環境にやさしい住まいです。
雨水タンクを設置して、雨水をトイレの水や屋根に流して夏場の暑さ対策に活用するなど、自然エネルギーを有効に利用したエコロジーな暮らしも提唱しています。
デザインは、江戸の“粋”を大切にしています。
江戸時代の暮らしから学びながら暮らそうというコンセプトで、4畳半+4畳半の小上がりの畳コーナーとダイニングは、夏は今のように開放的に、冬は小上がりの建具をしめて空間を分けて暖かく過ごすことができるようにしています。

適材適所で無垢材を活用
――モダンで洗練されたデザインが、とても素敵です。自然素材のひとつとして、無垢材をふんだんに取り入れたお住まいになっているのですね。どういった材種が使われていますか?K:木材は、宮城県栗原市と埼玉県飯能市の山の産地と協力しながら、国産材を使った家づくりをしています。宮城県とは、もう20年来のつきあいです。
それぞれ材種の特徴をふまえて、使い分けをします。建築主さまのお好みと予算に応じて選んでいきますが、私自身は個人的にスギが好きなので、スギが多めになっています。
材種別にご説明しましょう。
松(マツ)
この家の床はカラマツ、建具はマツです。針葉樹のマツは、柔らかくて足腰に負担がかからないので、お年寄りの住宅の床にはオススメです。材料は違いますが、感じとしてはコルクタイルのようなものです。マツは、赤みが強くなります。

杉(スギ)
壁、天井、柱にスギを使っています。白みが強く、経年で年輪のところに赤みが出てくるのが味わいです。ここの天井は、2階の床を兼ねた杉のパネルです。梁を隠さず、大工さんの技を堪能できるのと、天井高を実現しています。

2階の床を兼ねた一階の天井は、スギのパネル
檜(ヒノキ)
上がり框(かまち)にはヒノキを使っています。昔から日本で手に入るまっすぐな木材は、スギとヒノキだったため、柱にはスギかヒノキが使われてきました。ヒノキは、白みがいっぱいです。

小上がりの上がり框はヒノキ。上がり框の下は、奥行60cmくらいの収納になっている
楢(ナラ)・タモ
広葉樹で、堅い木の雰囲気が好きな方に好まれます。黄色みが強く、明るい色が多いので若い方にも人気です。
水回りにも!
この家では、お風呂にも無垢材を使っています。

17年前の新築当時(写真提供:光設計)
浴槽は高野槇(マキ)の木のお風呂で、ふたはさわらの板。バスコートの床は、耐久性を持たせるために燻煙加工したくりこま杉。脱衣室の床は、藤タイルです。

籐の床タイル(現在)。下地はゴムになっていて、濡れた場合も拭くだけでOK 。経年して部分的に傷んだ場合は、その部分だけを張り替えることも可能

バスコート(現在)。汚れたときにはデッキブラシで掃除を。明るい木の色から、グレーに変わってきたくりこま杉の床
経年変化の楽しみ
K:同じ無垢でも種類を変えると雰囲気はがらりと変わります。また、最初は黄色かったり、白っぽかったりする色が、年が重なってくると美しく変わってくれます。飴色になる具合が、材種によって違うのも楽しみのひとつです。
17年前の新築当時


17年前のリビングダイニング。坪庭のヤマボウシがまだ小さい!(上2点の写真提供:光設計)
17年後の現在


美しく経年美化した現在。スギの天井、マツの床の赤みが際立つ
無垢材のお手入れ方法とは?
――写真で比べて見ると、美しく色が変化していて驚きます! 美しい経年変化を楽しむためにも、無垢材はお手入れが必要でしょうか?K:自然素材だからといって、そんなに気を使ってメンテナンスをする必要はありません。この家では特に磨き込んだりなどはしておらず、自然の変化で飴色に変わってきた状態です。
メンテナンスは、床については水をはじくよう半年に一回くらいワックスがけを行います。雑巾がけの要領です。私は、天然原料で造るドイツの自然塗料メーカー・アウロのワックスをかけています。その他に特別なことはしていません。
また、自然素材の特徴として、木は生きているので湿度、熱の変化によって動くものです。
たとえば、この家のダイニングの床は床暖房になっています。湿度と熱の変化で、小さくなったり、大きくなったり。何年経っても、17年経った今でも動いています。でも、生活に支障がでるほどのことはありません。
そういうものとしてつきあっていく、自然素材の個性です。
自然素材にこだわるわけとは?
――長く自然素材の家づくりをしてきた理由をお聞かせください。K:もともとは自然素材の経年美化が美しいから自然素材の家を作っていましたが、15~20年くらい前から、シックハウスという問題に対して「自然素材の家」を提案してきました。
その自然な流れのなかで、省エネルギーな暮らし方を自然の素材を使った家づくりのなかで実現していきたいと思ってきました。
現代では法律が変わったり技術が変わったりして、防火地域、準防火地域でも4~5階建てのビルが木造で作れるようになってきました。学校や公共施設での木材使用も推奨されています。
輸入材に頼らず国産のもので賄うという機運もあり、需要が増えれば山の方も活性化してくると思います。
都会で木をつかうということは、産地の山を元気にすることでもあるし、木は二酸化炭素を吸って固定化していますので脱炭素にも貢献できることになります。
時代が変わりつつある、今がちょうど変わり目だと感じています。
――自然素材の無垢材を使うことで、持続可能な社会にも貢献できるのですね。本日は、ありがとうございました。
光設計について
一級建築士事務所(東京都世田谷区)自然素材、国産材を活用した家づくりを続けて30年以上。コモン(共有・共用地)の考え方を取り入れた分譲地「江戸Styleの家づくり(入会地による雑木林の町角づくり)プロジェクト」が平成21年度国土交通省長期優良住宅先導的モデル事業に採択された。
https://www.kokyusumai.com/
必要事項をご記入の上、
「資料を請求する」を押してください。
※は必須入力項目です。
【プライバシーポリシー】
個人情報の利用目的
このフォームに入力いただきました個人情報は、資料のお届けのほかに、以下の目的で利用させて頂く場合がございます。
- ①当社事業(不動産分譲事業、注文建築事業)等の営業活動における訪問、ダイレクトメール、電話、電子メールによる勧誘
- ②顧客動向調査、商品開発等の為の分析
- ③当社の商品やサービスの紹介や宣伝
- ④アフターサービス、定期メンテナンスの為の工事委託
- ⑤保険媒介代理事業
- ⑥ローン媒介代理業務
- ⑦その他当社の事業に付帯・関連する事項
その他個人情報の取り扱いについては、当社HPにてご確認ください。
https://www.aidagroup.co.jp/company/info/privacy.html