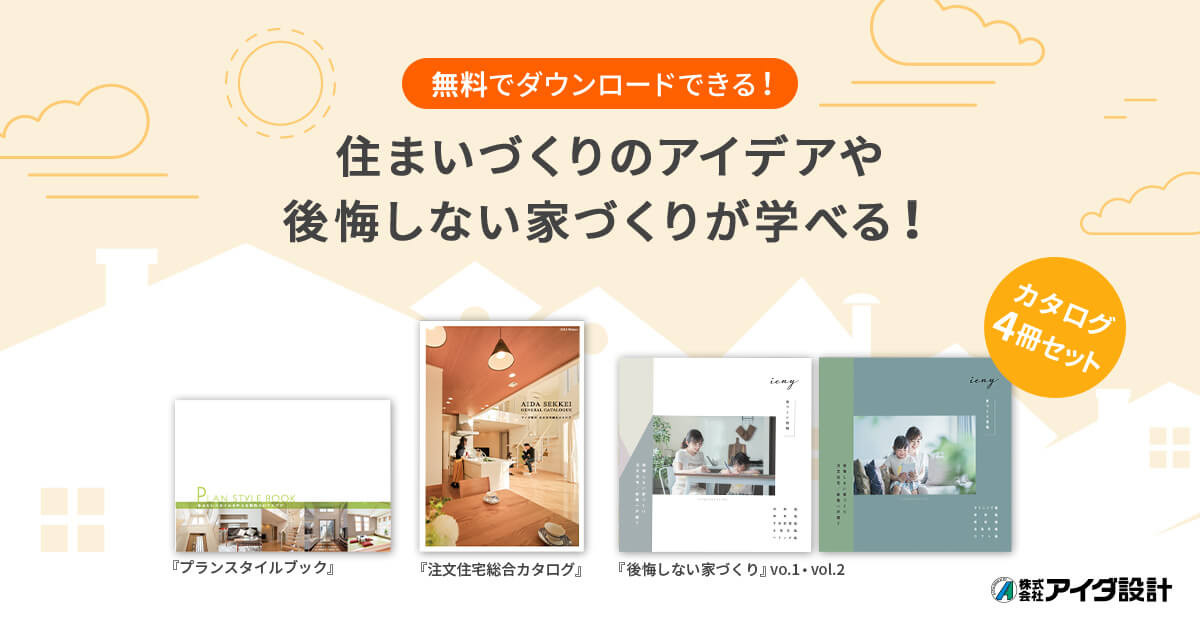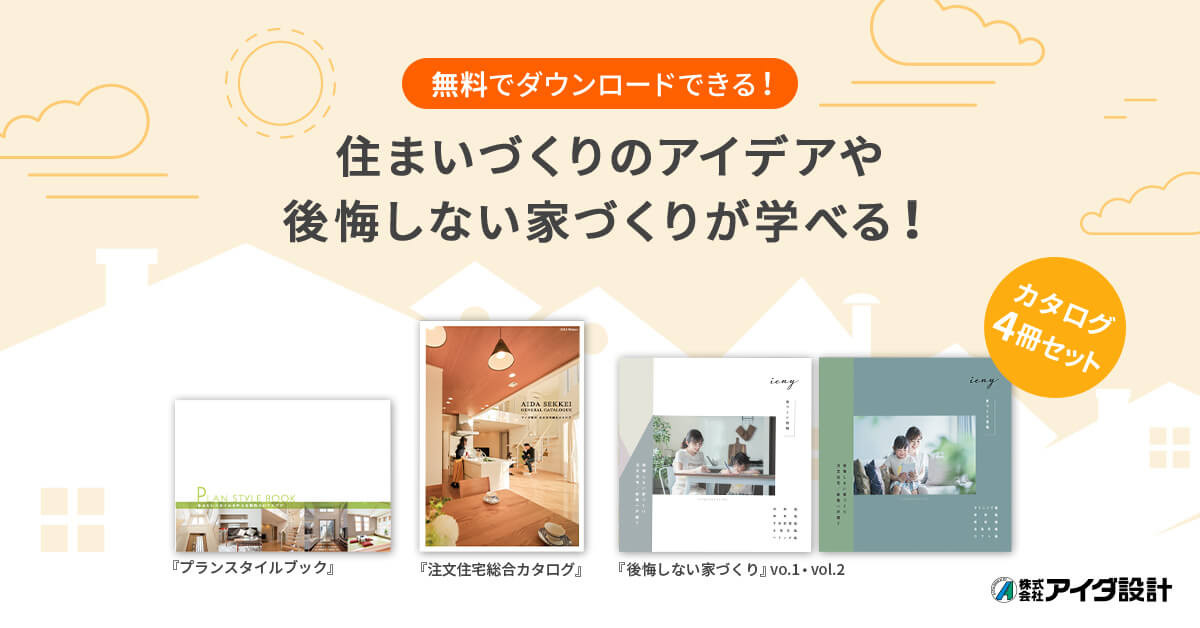住居学で学んだマイホームの守り方 ~フィッシュバーン流「家育て」vol.44~
こんにちは、フィッシュバーンです。
地球温暖化の影響だと思われる最近の異常気象、困りますね……。酷暑にあえいだら、お次は線状降水帯の大雨やら台風。やれやれ。
わが家は一度、台風で屋根が飛び、強烈な雨漏りを経験したため、大雨や台風と聞くと、そわそわしてしまいます。屋根修理後は、もう雨漏りをすることはなくなったのですが、未だなんとなく不安。

すっかりトラウマになってますね(笑)
その授業の中で、社会資本の一つである住宅を、資産として後世へ引き継ぐためにどう考えたらいいのか? という課題があり、自分なりの考えを図で描きました。

手書きでごちゃごちゃしていますが、先生にはお褒めいただき、A +の成績をいただいたので、考え方は間違えていないはず……。
この図を簡単に説明すると
「しっかり手入れし、管理してきた住宅は、自分の資産として価値が上がるだけでなく、社会の資産としても価値がある存在になる」
ということです。
住宅は、“建てたら建てっぱなし”では、その資産価値を守ることはできず、社会にとっても資産とはならないんですよね。
私にとって、わが家は夫なので(笑)、日々お世話をするのが日課。日頃の掃除、小さな補修、大きな修繕は、人間で言えば日々の養生、定期健診、診察や処方などにあたりますね。
こういう日々の管理をちょっとサボると、こんなことが起きます。

なんと、おせんべいのかけらに群がるアリさんたちを発見! それも、これは3階の部屋の床。一体どこから3階に??
この現状の問題点は2つ。
まだまだわが家(夫)への気配りが足りませんね……。早速、アリ退治グッズを買い込みました(笑)
3人が暮らす建築物で、場所は都心住宅地、敷地面積、建ぺい率など、条件が決まった中での設計課題。

地下1階、2階建て。3室の賃貸住居のある建物。

共有の庭もあり、2階の部屋は大きな窓が特徴。

地下の部屋も日差しが入るように設計しました。
この授業、受講している生徒は約100人。10人ずつくらいに分かれてスタディをするのですが、最終的な発表の際、一つとして全く同じプランがないことに驚かされました。
つまり、住宅への希望や案は、“100人いたら100通り”ということですね。
中には、ぜひ住んでみたいと思うような素敵なプランから、ひたすらデザイン性重視で、これ大丈夫? と思うようなプランもありました(笑)
私は、実際に住むなら……を考え、動作がしやすく安全で無駄のないサイズ感、敷地に余裕を持ち、周辺環境に馴染む、そんなことを意識してプランを作りました。
とりわけ意識をしたのは、居住者とともに、周囲にも安全であること。自分の家だけがよければそれでいい、という考え方はいかんですよね。
住居は、人が日々暮らし、そこに安心を求めるもの。そして安全であることは安心を生む。
すべての建築物は、誰かが使用する限り、安全でなければなりません。
そういえば、先日、築年数の古い建物の内部で、こんなものに出会いました。

こうやって古い建物の柱と梁が、特殊な金物で補強されている姿を見て、小さな安心安全を感じました(笑)きちんと管理が行き届いています。
皆様、安全で価値のあるマイホームであり続けるために、維持管理がんばりましょうね。
地球温暖化の影響だと思われる最近の異常気象、困りますね……。酷暑にあえいだら、お次は線状降水帯の大雨やら台風。やれやれ。
わが家は一度、台風で屋根が飛び、強烈な雨漏りを経験したため、大雨や台風と聞くと、そわそわしてしまいます。屋根修理後は、もう雨漏りをすることはなくなったのですが、未だなんとなく不安。

すっかりトラウマになってますね(笑)
マイホームの価値を守るためには……
昨年から大学で建築や住居学を学び、住宅の構造、施工方法、法律、管理の仕方やその大切さなど、多くを勉強しています。その授業の中で、社会資本の一つである住宅を、資産として後世へ引き継ぐためにどう考えたらいいのか? という課題があり、自分なりの考えを図で描きました。

手書きでごちゃごちゃしていますが、先生にはお褒めいただき、A +の成績をいただいたので、考え方は間違えていないはず……。
この図を簡単に説明すると
「しっかり手入れし、管理してきた住宅は、自分の資産として価値が上がるだけでなく、社会の資産としても価値がある存在になる」
ということです。
住宅は、“建てたら建てっぱなし”では、その資産価値を守ることはできず、社会にとっても資産とはならないんですよね。
私にとって、わが家は夫なので(笑)、日々お世話をするのが日課。日頃の掃除、小さな補修、大きな修繕は、人間で言えば日々の養生、定期健診、診察や処方などにあたりますね。
こういう日々の管理をちょっとサボると、こんなことが起きます。

なんと、おせんべいのかけらに群がるアリさんたちを発見! それも、これは3階の部屋の床。一体どこから3階に??
この現状の問題点は2つ。
- 私が掃除をきちんとできていないこと
- 家の中にアリが入って来る隙間があること
まだまだわが家(夫)への気配りが足りませんね……。早速、アリ退治グッズを買い込みました(笑)
「安全」はすべての建築物にとって最も重要なこと
設計の授業で小さな共同住宅をプランしました。3人が暮らす建築物で、場所は都心住宅地、敷地面積、建ぺい率など、条件が決まった中での設計課題。

地下1階、2階建て。3室の賃貸住居のある建物。

共有の庭もあり、2階の部屋は大きな窓が特徴。

地下の部屋も日差しが入るように設計しました。
この授業、受講している生徒は約100人。10人ずつくらいに分かれてスタディをするのですが、最終的な発表の際、一つとして全く同じプランがないことに驚かされました。
つまり、住宅への希望や案は、“100人いたら100通り”ということですね。
中には、ぜひ住んでみたいと思うような素敵なプランから、ひたすらデザイン性重視で、これ大丈夫? と思うようなプランもありました(笑)
私は、実際に住むなら……を考え、動作がしやすく安全で無駄のないサイズ感、敷地に余裕を持ち、周辺環境に馴染む、そんなことを意識してプランを作りました。
とりわけ意識をしたのは、居住者とともに、周囲にも安全であること。自分の家だけがよければそれでいい、という考え方はいかんですよね。
住居は、人が日々暮らし、そこに安心を求めるもの。そして安全であることは安心を生む。
すべての建築物は、誰かが使用する限り、安全でなければなりません。
そういえば、先日、築年数の古い建物の内部で、こんなものに出会いました。

こうやって古い建物の柱と梁が、特殊な金物で補強されている姿を見て、小さな安心安全を感じました(笑)きちんと管理が行き届いています。
皆様、安全で価値のあるマイホームであり続けるために、維持管理がんばりましょうね。
必要事項をご記入の上、
「資料を請求する」を押してください。
※は必須入力項目です。
【プライバシーポリシー】
個人情報の利用目的
このフォームに入力いただきました個人情報は、資料のお届けのほかに、以下の目的で利用させて頂く場合がございます。
- ①当社事業(不動産分譲事業、注文建築事業)等の営業活動における訪問、ダイレクトメール、電話、電子メールによる勧誘
- ②顧客動向調査、商品開発等の為の分析
- ③当社の商品やサービスの紹介や宣伝
- ④アフターサービス、定期メンテナンスの為の工事委託
- ⑤保険媒介代理事業
- ⑥ローン媒介代理業務
- ⑦その他当社の事業に付帯・関連する事項
その他個人情報の取り扱いについては、当社HPにてご確認ください。
https://www.aidagroup.co.jp/company/info/privacy.html